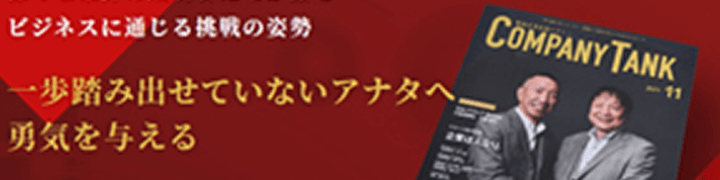巻頭企画天馬空を行く

元スピードスケート選手 / 実業家
清水 宏保
 1974年、北海道帯広市出身。3歳からスケートを始め、1991年 に日本高校新記録(500m)を出し、さらに全日本スプリントで総合4位に入賞し脚光を集める。1993年には18歳でワールドカップ初出場初優勝という快挙を成し遂げ、世界のトップスケーターの仲間入りを果たした。その後、長野オリンピック500mで金メダル、1000mで銅メダル、ソルトレークシティーオリンピックで銀メダルを獲得するなど、長年にわたって世界のスピードスケート短距離界の第一人者として活躍を続ける。2010年3月に現役を引退した後は、札幌市にリハビリ・通所介護事業、訪問看護事業、フィットネススタジオ事業、高齢者住宅事業など多角的にサービスを提供する(株)two.sevenを設立し、経営者として積極的に活動。また、講演会の出演や執筆活動など、文化人としての顔も持つ。
1974年、北海道帯広市出身。3歳からスケートを始め、1991年 に日本高校新記録(500m)を出し、さらに全日本スプリントで総合4位に入賞し脚光を集める。1993年には18歳でワールドカップ初出場初優勝という快挙を成し遂げ、世界のトップスケーターの仲間入りを果たした。その後、長野オリンピック500mで金メダル、1000mで銅メダル、ソルトレークシティーオリンピックで銀メダルを獲得するなど、長年にわたって世界のスピードスケート短距離界の第一人者として活躍を続ける。2010年3月に現役を引退した後は、札幌市にリハビリ・通所介護事業、訪問看護事業、フィットネススタジオ事業、高齢者住宅事業など多角的にサービスを提供する(株)two.sevenを設立し、経営者として積極的に活動。また、講演会の出演や執筆活動など、文化人としての顔も持つ。
幼い頃からぜんそくに苦しみ、また162cmと小柄な体格ながら、長野オリンピック500mで日本スケート史上初の金メダルを獲得するなど、数々の偉大な記録を打ち立てたスピードスケート界のパイオニア。それが、不屈の闘志で数々の逆境に立ち向かい、「神の肉体を持つ男」とも称された清水宏保氏だ。引退後は大学院で医療経営学を学び、現在は故郷の北海道で介護関連企業経営者として活躍する同氏。アスリート時代に飛躍的に成長できた理由からスポーツと会社経営の共通点まで、飾り気のない、核心を突くような言葉で存分に語ってくれた。
きついトレーニングが当たり前だった
スピードスケート短距離界の第一人者として長年にわたり世界の第一線で活躍し続け、日本が誇るトップスケーターであった清水宏保氏。そんな同氏がスケートを始めたのはわずか3歳の時だった。北海道帯広市の出身であり、自身が生まれ育った環境がその後のスピードスケート人生を大きく左右したという。
「今から振り返ると、やはり幼少期を北海道で過ごしたというのは大きかったですね。もしこれが他の地域だったら、幼くしてスケートと出合うことはなかったと思います。特に私の故郷である帯広市では小学校の授業でスケートを行っていたので、自分にとっては物心ついた頃からとても身近なスポーツでした。兄は柔道とレスリングを、姉はアイスホッケーをやっていたんです。そのような環境にいたこともあり、私もまたスケート以外に、剣道や柔道、サッカーやレスリング、スキーなどさまざまなスポーツを経験しました。その中で、特に『楽しい』と感じたのがスケートとスキーだったんです。その理由は、ひと言で言うとスピード感を実感できたからでした。日常生活の中では決して味わうことができない体感スピードのとりこになったというわけです。さらにスケートに関しては、時間(=記録)と戦うのが非常に楽しかった。私は子どもの頃から人と争うことが、とりわけ荒々しい競争が性格的に苦手だったんです。最初は持病のぜんそくを治すことを目的に、運動療法の一環としてスケートを始めました。子どもの頃は、父と2人で、冬はスケート、夏は自転車などでロードに出かけましたが、とにかくハードなトレーニングでしたね。でも、徐々に慣れてくるとそのきつさが自分の中で標準化されていき、試合での良い結果に結びついていったように感じます。もし緩い環境でトレーニングを続けていたら、その緩さが自分の標準になってしまう。そうならなくてよかったと思っています。つらいことが当たり前であり、デフォルトである、と。当時の経験がその後のスケート人生にプラスに作用したことは間違いありません」
ぜんそくで体調の変化に敏感になった
清水氏にはぜんそくに関する著書『ぜんそく力 ぜんそくに勝つ100の新常識』(出版社:ぴあ)もあり、同じく少年時代にぜんそくに苦しんでいたフィギュアスケート選手の羽生結弦氏は同氏の言動に勇気づけられたという。スポーツ選手にとってぜんそくを患うことは不利だと言われることが多い。ぜんそくが持病であることが清水氏の人生、とりわけアスリート人生にどのような影響を与えたのか聞いてみた。
「前述したようなきわめてハードだった父との練習と同様、ぜんそくを患うことで肉体的にも精神的にもつらいのが自分の中で標準になったという点がまず大きかったですね。あとはそれとも関係しますが、日頃からいつも自分の体と向き合わざるを得ないということでしょうか。例えば、誰しも風邪をひいて喉が痛くなれば、意識が喉に向きますよね。でも往々にして、人は健常時には自分の体に関心を持ちません。ぜんそくというのは、ほこりや空気の変化など環境因子によって起こるものなんです。そのため、自分の体に対して自然に興味を持つようになり、体調の変化について誰よりも敏感に感じることができたのだと思います。またそれに伴い、フィジカル・トレーニングに関しても常に自分の体の状態を意識しながら取り組むようになったんです。そのせいか、現役時代はとにかく感覚が異様に鋭かったですね」
橋本聖子氏の言葉でプロを意識し始めた
中学からスケート部に入部し、高校はスケートの名門である白樺学園高校のスポーツ科に進学した清水氏は、浅間選抜500mで日本高校新記録を出し、高校3年生の時にはインターハイの500mと1500mを制覇。さらに大学1年時の1993年にはわずか18歳でスピードスケートワールドカップに初出場し、初優勝という快挙を成し遂げた。まさに順風満帆だった当時の同氏は、どのような目標を掲げていたのだろうか。
「学生時代の私は何も考えず、無我夢中で毎日の練習に打ち込んでいましたね。ただ、高校1年生の時に、当時指導してくれていた先生から『まずは目標を書きなさい』と言われました。要するに、目標設定を明確にしろというわけです。入学して1年目の目標を決め、次に高校3年間の目標を実現可能かどうかは関係なく、少し大きめに設定するように指示されました。それで私は、高校1年生はインターハイのレギュラーになること。2年生はインターハイで優勝する。3年生の時はちょうどオリンピックイヤーだったので、オリンピックに出場することを目標にしたんです。すると、それらの目標が自分の潜在意識に植え付けられ、実際に2年生まではその目標を達成できました。さらには、3年生の時もオリンピック出場の一歩手前までいけたんです。そのように、自らが設定した目標と現実が次第にリンクするようになるにつれ、正直、戸惑う部分もありました。まだ心の準備が、もっと言えば覚悟ができていなかったからです。当時はプロスケーターになることはあまり意識していませんでした。本格的にプロを意識するようになったのは、私が最初に出場したオリンピックであるリレハンメルオリンピック(1994年2月開催)が終わった後のことだったと思います。その頃は大学卒業後の進路について、実業団など多方面からお話をいただくようになっていました。そうした状況の中で『自分はこの先どうしていきたいのか』を考え始めるようになっていた時に、オリンピックの選手村で偶然、同じ北海道のご出身でスピードスケートの大先輩でもある橋本聖子さんとお会いしたんです。その時に、進路について悩んでいることを伝えたら、橋本さんは『プロになる道もあるんじゃない?』とおっしゃいました。ただし、プロになるためには、4年後の長野オリンピックで金メダルを獲得することが最低条件であることを付言されたんです。『もし金メダルを取ることができれば、その次の展開が見えてくる』というのが橋本さんのお考えだったので、私はその時からプロになることを意識し始めました」
最も印象深いのは長野オリンピック
橋本聖子氏が言う「プロになるための最低条件」であった長野オリンピックでの金メダル獲得という目標を達成した清水氏は、4年後のソルトレークシティーオリンピックで激しい腰痛に苦しみながら銀メダルを手にした。2006年トリノオリンピックと合わせて計4度出場したオリンピックの中で、同氏が特に印象に残った大会について質問すると――
「やはり最も印象深いのは金メダルを取った長野オリンピックで、その次がソルトレークシティーオリンピックですね。私の中で、前者はとても良い思い出ができたオリンピックであり、後者は苦労した経験が多かったオリンピックという位置づけになります。ソルトレークの時はとにかく『これで自分のスケート人生が終わってもいい』というくらいの気概で試合に臨みました。あの時はまともにズボンも靴下もはけないほどの極度の腰痛に悩まされましたが、オリンピックという最高峰の舞台だったこともあり、辞退するという選択は一切頭をよぎりませんでしたね。もちろん、いずれも違った環境で挑んだオリンピックですので、4度すべてにそれぞれ思い出があることは間違いありません」
「ゾーン」を体験すると良い結果を生む
金メダルを獲得することによって、まさしく世界の頂点へと上り詰めた清水氏だが、その直後に「何かが違うんです。長野オリンピックで極めたとは思わなかった。僕の目的は簡単に言うなら、自分の体を通して人間の可能性を探りたいということなんです」とコメントしている。常人にはにわかに理解できない内容の発言だが、同氏はなぜそのような心境に至ったのだろうか。
「いろいろなレースをしている中で時折、集中力が非常に高まり、周囲の景色や雑音などが意識の外に排除されると、自分の感覚だけが異様に研ぎ澄まされ、レースに没頭できる特殊な意識状態――いわゆる『ゾーン』というものを体験することがあるんです。しかし、それはあくまで偶発的なものであり、事後的にはなぜそういう状態になったのかはわかりません。でも、そのような『ゾーン』を体感する時というのは、往々にして良い結果が生まれるものなんです。『もし、意図的にゾーンに突入することができたらどんなレースでも優位に立つことができるはずだ』と感じていたので、当時はそのような心境になったのだと思います。スピードスケート選手として経験を重ねていくうちに、そうしたものを追い求めていくようになったんです。スピードスケートの特徴の1つとして、他の競技と比べると試合数が少ない点が挙げられます。例えばプロ野球のように連日試合があれば、日々いろいろなトライアンドエラーを繰り返せるのでしょうが、スピードスケートは多くてもせいぜい週に1試合あるかどうかです。だからこそ、1試合1試合に深く集中することができたのだと思います。もしかしたら、試合数が多すぎると毎試合同じように集中するのが難しいかもしれません。数少ない舞台、限られたチャンスの中で最高のパフォーマンスを披露したい、という気持ちが強かったのでしょう。それから、試合の時は少し引いた目線で状況をとらえるという、俯瞰的視点を持つようにも心がけていました。リレハンメルオリンピックで思うような結果が残せなかった時から、意識して自分を客観視するようになった気がしますね」