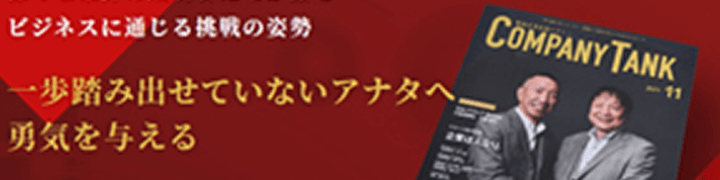巻頭企画天馬空を行く

![]()
駒田 徳広
NORIHIRO KOMADA
 1962年9月14日、奈良県出身。奈良県立桜井商業高等学校を卒業後、1980年にドラフト2 位指名を受けて読売ジャイアンツ(巨人)に入団する。3年目から一軍に定着して実績を積み、1994年にFA 権を行使し横浜ベイスターズへ移籍。満塁時の打席で抜群の勝負強さを見せ、「満塁男」と称された。2000年に2000本安打を達成し、同年に現役引退。その後は野球評論家として活動する一方、2005年から東北楽天ゴールデンイーグルス、2009年からベイスターズの打撃コーチを歴任。2012年9月から常磐大学硬式野球部の臨時コーチを務め、同年にチームは3 季ぶりに関甲新学生野球連盟一部リーグへの昇格を決めた。また、2016年から2019年まで、独立リーグ・高知ファイティングドッグスの監督を務めた。2020年9月に、巨人時代の先輩・西尾亨氏と共同経営で「Koma’s House」を開店。
1962年9月14日、奈良県出身。奈良県立桜井商業高等学校を卒業後、1980年にドラフト2 位指名を受けて読売ジャイアンツ(巨人)に入団する。3年目から一軍に定着して実績を積み、1994年にFA 権を行使し横浜ベイスターズへ移籍。満塁時の打席で抜群の勝負強さを見せ、「満塁男」と称された。2000年に2000本安打を達成し、同年に現役引退。その後は野球評論家として活動する一方、2005年から東北楽天ゴールデンイーグルス、2009年からベイスターズの打撃コーチを歴任。2012年9月から常磐大学硬式野球部の臨時コーチを務め、同年にチームは3 季ぶりに関甲新学生野球連盟一部リーグへの昇格を決めた。また、2016年から2019年まで、独立リーグ・高知ファイティングドッグスの監督を務めた。2020年9月に、巨人時代の先輩・西尾亨氏と共同経営で「Koma’s House」を開店。
本誌でゲストインタビュアーを務める野球評論家の駒田徳広氏。現役時代には、満塁時に無類の勝負強さを発揮し、2000 本安打を達成して名球会に入会。守備面でも一塁手として史上最多となる10 度のゴールデングラブ賞を受賞し、輝かしい成績を残した。自身を「異端児」と称するなど、人間味のある一筋縄ではいかないそのキャラクターに魅了されたファンも多い。客観的な自己分析に裏打ちされた独自の思考法は今も健在だ。野球に対する思いからメンタルコントロールの方法、組織論まで、率直な言葉で飾らず語ってくれた。
![]()
始まりは祖父とのキャッチボール
選手として、解説者として、指導者として、長年にわたって野球と関わり続けてきた駒田氏はどのようにして野球と出会ったのか。まずはその原点について聞いてみた。
「幼稚園の年中の時に、母方の祖父が『キャッチボールをしよう』と言ってきたんです。最初はよくわからないままにやっていましたが、何となくおもしろいと感じていました。それで年長になった頃、通っていた幼稚園の運動場で近所の小学生が草野球をしていたので、その中に入れてもらい、一緒にやっているうちに本格的に野球のおもしろさに目覚めたんです。小学校1年生の時には『あの子は野球がうまい』と周囲で評判になり、ちゃんとした野球をやるようになっていきました。記念すべき初打席がデッドボールだったことを覚えています(笑)。二打席目はレフトオーバーの二塁打でした。相手は全員小学校3、4年生で年上なのに、『あまりうまくないなあ』と思っていたんです。なので3年生くらいになると、6年生と一緒にやるようになりました。子どもの時はひょろっとした体型でしたが、スポーツは全般的に得意でしたね。小学生の時は野球以外にも陸上と水泳もしていて、水泳に関しては奈良県で2、3番目くらいに速かったんですよ。その後、中学校に入ったところで、野球一本でやっていくことを決めました。体が大きかったこともあって、ポジションはピッチャーでしたね」
プロ初打席で満塁ホームランの快挙
高校時代にはエースで4番打者として活躍。甲子園には出場できなかったものの、高校通算で43本塁打、打率4割9分を記録し、1980年にドラフト2位で巨人に入団した。そしてプロ入り3年目の1983年に、日本プロ野球史上初となるプロ初打席で満塁ホームランを放つという鮮烈なデビューを飾ることになる。
「あの時のことは今もよく覚えていますよ。それまでの2年間、2軍でそれほどいい成績を残せていませんでした。ただ、2年目のシーズンでホームラン7本を記録し、そのうちの3本が対戦相手の右田一彦投手から打ったものだったんです。ですから、デビュー戦で非常に相性の良いピッチャーと対戦することになった。もちろん、それだけの理由で打てたとは思いませんが、運が良かったことは確かですね。その後も満塁時に好成績を残すことになりましたが、最初は運と縁に助けられて満塁ホームランを打っていたと思います。けれど、人間というのは打てば打つほど、どのようなプロセスを経れば好結果につながるかというのを徐々に習得していくわけです。満塁というのは、フォアボールになると1点を失う状況なので、ピッチャーはどこかのタイミングでストライク勝負をしなければいけない。僕は今でも何を考えているのかわからないとよく言われるのですが、毎試合、自分が何をすべきかというプログラムをきちんと組み立てたうえで打席に立っていました。その中でも満塁というのは自分が一番勝負しやすい状況だったんですよ。例えばランナー2、3塁というケースなら、ベースが1つ空いているので、投手はフォアボールで逃げるという戦略を組めるわけです。しかし満塁だとそうはいきません。最終的にはピッチャーが勝負してくれるという状況が、自分の思考と合っていたんでしょうね」
恩師から学んだチームプレーの大切さ
背番号50だった駒田氏はこの年、背番号54の槙原寛己氏、55の吉村禎章氏と共に「50番トリオ」と呼ばれ、巨人のセ・リーグ優勝に貢献。やがて松原誠コーチの指導により自分に合った打撃スタイルを確立し、チームに欠かせない選手となっていく。巨人時代、特に大きかったのが藤田元司監督の存在だったという。
「藤田監督は、自分が選手に望むことを僕らに対して非常に明確に伝えてくれる方でした。別の言い方をすれば、どういうことをしたら監督が嫌がるかということもわかってしまうわけですよ。人間というのはかわいがってもらえばもらうほど、その人の顔色を見るようになるものです。僕は藤田監督にとてもかわいがってもらったので、いつも『この監督は何を思っているのかなあ』と考えるようになりましたね。そのような影響を与えてくれたというのは僕の人生にとってもすごくプラスのことですし、『野球はみんなでやるものなんだよ』という一言も、藤田監督の人間性から湧き出る言葉だということがよくわかっていたので、監督の駒になりたいと自然に思うようになっていきました。『監督の駒』になるということはイコール、チームプレーでもありますし、そうすることによってチームへの貢献にもつながるわけです。それから、藤田監督はとにかく褒めるのが上手でした。選手を叱るのはいつもコーチ(笑)。例えば、コーチに叱られて帰ってきて、たまたまお風呂で一緒になると、『元気がないじゃないか。コーチにいろいろ言われたな』と笑いながら言うんですよ。そういったバランスの取り方が絶妙でしたね。藤田監督が怒るのは、チームの和を乱すとか、試合を投げ出してしまうとか、決して許されない行為をした時だけでした。だから僕は『絶対にこの人を怒らせてはいけない』と思っていましたね」
新天地・横浜で感じた巨人とのギャップ
1990年には七番打者ながらチーム最多の本塁打と打点を記録し、セ・リーグ二連覇に貢献。1992年には、原辰徳氏、斎藤雅樹氏と共に日本人としては巨人初の年俸1億円プレーヤーとなった。そんな駒田氏にとって1994年に大きな転機が訪れる。それがFA宣言をしての横浜ベイスターズへの移籍だった。この年、駒田氏は32歳を迎えてチーム最年長に。どのようにして新天地になじんでいったのだろうか。
「移籍による苦労はそんなにありませんでした。やれることは決まっていますから。ただ、少し嫌だったのは、僕の口から出てくる言葉というのは、すべて巨人での経験によって培われたものなので、それを毛色の異なるベイスターズの組織に直接ぶつけても、うまくいかなったことです。極端にいえば『優勝しようよ』と口にしても、そういう気持ちが本当に湧き出てこないかぎりは、僕が言ったって『ここは巨人じゃないんだよ』という話になってしまう。だから、最初のうちは多少話をさせてもらうことはありましたが、だんだん言わなくなりましたね。試合に勝つには、そのための方法を自分たちで探し出さなければいけないなと思っていましたので」
キャプテンとしての重圧はなかった
1998年にはキャプテンに就任し、五番打者としてチーム38年ぶりの日本一に貢献。日本シリーズでは優秀選手に選出され、ベストナインにも初選出と、セ・リーグを代表する一塁手になった。しかし、そんな状況でも駒田氏はキャプテンとしてのプレッシャーはなかったと話す。
「キャプテンという肩書は、球団が公認したというわけではなく、選手間だけで決めたものだったんです。僕は意外と神経質なところがあるので、『キャプテン』という言葉を口にすると、チームを日本一に導いたことの対価を要求しているのではないかと思われるのが嫌でした。シーズン中も、それほどキャプテンらしい扱いを受けていませんでしたからね。キャプテンを務めたことによる報酬をもらおうとはまったく思っていなかった。チームが優勝できたのは、やっぱり若い選手たちが力をつけてくれたからだと思います。彼らと一緒になってやっていけるベースができてきたという感触を持てるようになりました」