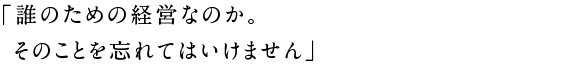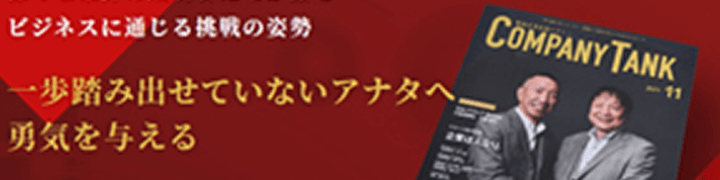巻頭企画天馬空を行く
![]()

物のサービスに頼らない営業が本道
高校を卒業し、大手不動産会社で働いていた宗次氏は、1973年、23歳の時に独立して不動産業を興す。1年半営業する中で、4棟の建売住宅を販売したという。それにより十分な利益が得られ、上々のスタートである。
だが宗次氏はそのまま不動産業を続けようとは思わなかった。夫人の社交的な性格を活かしたいと考え、喫茶店「バッカス」をオープン。当時は今と違って外資系のカフェなどほとんどない。そう考えれば勝機があったように思えるが、名古屋市には喫茶店が他県よりも多く、当時から競争は激しかった。
と言うのも、名古屋市近郊は安価で朝食を提供する「モーニング」サービスの発祥地として知られるほど、多くの市民がモーニングを好む。だから名古屋市の喫茶店にモーニングをメニューに載せていない店はほぼない。
ところが宗次氏はモーニングを提供しなかった。「バッカス」が開店当初、苦戦していたのはこのためだ。客も友人も、経営相談に乗ってくれた人も「モーニングを今すぐ始めなさい」と助言したという。
どうしてモーニングサービスを提供しなかったのか。「モーニングは物のサービスだ」と宗次氏は言う。本来、300円の価値のあるものに、「おまけ」の商品を加えるのは、いくらサービスといえども実際は安売りと同じだ。1個300円の商品を2つで500円にして売るのは物販の常套手段だが、見た目には売り上げが上がっても、数字だけ見れば1個につき50円の値引きをしているのと同じである。
ただ、宗次氏は「安売り」を避けたかったのではない。「物や安売りのサービスに頼らないと売れない」ことに違和感を抱いたのだ。だから宗次氏は、他店では無料でついてくる「おつまみ」にも30円の値段をつけた。
モーニングサービスの聖地で、モーニングなしの営業をするのだ。当然それに代わる何かを見出さないことには客足は遠のくばかり。
では宗次氏は何をもって「物のサービス」の代わりとしたか。それは「明るい店、笑顔で溢れた店」という接客面でのサービスだった。
まだ「顧客満足」という言葉もなかった当時、顧客本位のサービスを貫き、一人ひとりの客に柔軟な対応を心がけるという経営方針は、客の心を掴み、店を繁盛店へと成長させる。
そしてさらなる売上拡大を図り、喫茶店にてカレーの宅配サービスを開始、大きく売り上げを伸ばした後も、顧客第一の接客を変えなかった。喫茶店を閉め、カレー専門店「カレーハウスCoCo壱番屋」で勝負しようと決めてからも、この方針を貫き続けた。
飲食店を経営するオーナーであれば「明るい店、笑顔で溢れた店」が店づくりの基本であることは当然知っている。しかし、はたして実践できている店がどれだけあるだろうか?ましてや当時、宗次氏が行っていたように、客が来るたび帰るたび、経営者自身が心からの感謝をもって挨拶をしてくれる店は決して多くなかっただろう。最近では「頑固親父の無愛想」が名物になっている店も少なくないが、これは、客商売で最も大切なことがおろそかにされているだけではないだろうか。飲食店は製造業ではない。あくまで接客業だ。
自分の店に思い入れを持つ
最近の飲食業界では「スクラップアンドビルド」の経営方針が主流だ。これは採算の合わない店舗はすぐに閉め、代わりに新しい店を次々と出店する手法のことを指す。
資金力のある大手企業がこれを行うのはいい。宗次氏が引退した後の「壱番屋」もこの方針で世界も含めてチェーン展開している。しかし最近では個人事業主までもがそれをしようとする。「決して間違った考えではないが、商売は誰のためにするものかを、今一度考え直す必要がある」と宗次氏は話す。
その地で商売を始めた以上、経営者には店を維持していく責任がある。例えば、ある地でスーパーマーケットを開いたとする。ところが予想に反して売り上げが伸びず赤字が続くと、最悪の場合「閉店」に追い込まれる。
しかし、そのスーパーマーケットを頼りにしている人はいるはずである。それがカレー専門店であれば、その店のカレーを食べたいと思っている客が必ずいるはずだ。「そうしたお客様のことを考えずに安易に店を閉めるのは無責任だ」と宗次氏は言う。
「店は経営者の利益のためにあるのではありません。お客様、従業員、その家族のため、しいては地域のために必要とされているのです」
宗次氏が「壱番屋」の経営を担っていた頃に創った店は全部で800店。そのうち閉店したのはわずかに2店舗だ。
こんなエピソードがある。某県にあった店をやむなく閉店することとなり、宗次氏は営業最終日、わざわざその店に出向いた。宗次氏はどうしても、自分の手で店を壊したかったのだ。それが店を創った者の責任であり、悔しさや無念を払拭するための唯一の方法だと考えたのである。
カナヅチとバールをバッグに入れ、出張先から新幹線に乗り込み、現地に着いたのが夜。その足で店に向かい、最後のお客様を「ありがとうございました」と自ら送り出した。翌朝、ホテルからタクシーでその店に向かうまでの間、タクシーの運転手は「壱番屋」の会長とは知らずこんな話をしてきた。
「あそこは立地が悪くて、今まで店ができては潰れ、できては潰れで長続きしなかったんだけど、CoCo壱番屋さんは頑張っているよ」
そう思ってくれる人がいたことを最後に確認できただけでも、宗次氏が現地に行った意義は大きかっただろう。