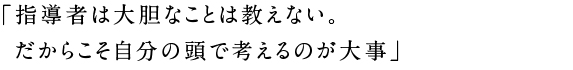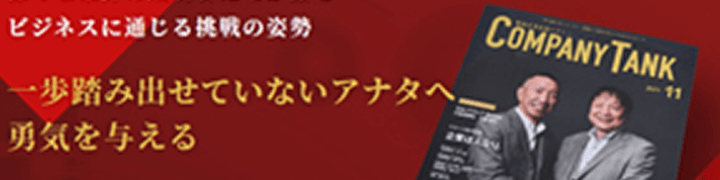巻頭企画天馬空を行く

![]()
梨田 昌孝 Nashida Masataka
元プロ野球監督 プロ野球解説者
1953年、島根県浜田市生まれ。島根県立浜田高校時代には3年の春・夏に甲子園出場を経験する。1971年にドラフト2位で近鉄バファローズに入団、強肩捕手として2年目から頭角を現し、1979年、80年のリーグ連覇に大きく貢献。ベストナイン(1979〜81)、ゴールデングラブ賞(1979〜81、83)を獲得するなど、リーグ屈指の好捕手として活躍する。1988年に現役を引退。1993年にコーチとして近鉄に復帰し、二軍監督を経て2000年に監督に就任、翌2001年にチーム4度目となるリーグ優勝を果たす。野球評論家としての活動を経て2008年、北海道日本ハムファイターズの監督に就任。翌2009年にリーグ優勝を果たした。2011年のシーズンを最後に現場を離れ、現在はプロ野球解説者として活動中。
2001年、大阪近鉄バファローズ。2009年、北海道日本ハムファイターズ。これは梨田氏が、プロ野球の監督として優勝に導いた年とチーム名だ。プロ野球史上、複数チームでの優勝を成し遂げた監督は王貞治氏・野村克也氏・星野仙一氏など10名しかおらず、これは監督としての実力はもちろんのこと、他球団からオファーされるだけの器量や人望がなければ為し得ない大偉業と言えよう。そんな梨田氏に、野球人としてどうチームと向き合ってきたのかについて、語って頂いた。
![]()
自ら編み出したオリジナル打法
大阪近鉄バファローズ・北海道日本ハムファイターズの2球団を優勝に導いた梨田氏。2球団以上を優勝させたプロ野球の監督は過去に10名いるが、監督の在籍年数が短くなりつつある昨今、2000年以降の達成者は梨田氏ただ1人というのは特筆すべき点だ。そんな名将・梨田氏のルーツに、まずは触れてみたい。
「僕が小学生の頃は、スポーツと言えば野球しかなかったからね、兄貴に混ざって町内会のソフトボール大会に出たりしているうち、なんとなく野球をやるようになったんです。『ボールを思いっきり投げる』『バットで遠くに飛ばす』という爽快さに惹かれましたね。ちょうどその頃は巨人の長嶋茂雄選手がヒーローでしたから、サードのポジションと背番号3は奪い合いでした(笑)。
僕の現役時代のポジションである“捕手”を始めたのは中学1年のとき。当時の監督が新入部員の約40名を背の順に並ばせ、高いほうから2名を投手に、3番目だった僕を捕手に指名したんです。『お前、キャッチャーな』って。正直、そんな安易に決められるなんて嫌だなと思いましたよ。やっぱりキャッチャーって、防具類を装着してひっきりなしに立ったり座ったりして体力的にきついし、頭も使う難しいポジションなんです。それでも捕手を続けるうちに愛着が湧いてきて、高校の野球部に入ったときにはキャッチャーしか考えられなくなっていました。というのは、性格的な部分で向いていると思ったからなんです。
ピッチャーはみんなお山の大将というか、ワガママな人種なんですよ(笑)。僕も投手というポジションに憧れたことはありましたが、どちらかと言えば皆をまとめるタイプだったし感情を抑えるのも苦じゃなかったから、むしろ捕手は自分に合っているポジションではないかと。結果的に捕手として注目してもらい、プロ野球の世界に進むことができたわけですから、この選択は決して間違いではなかったと思いますね」
偶然のなりゆきから“捕手”になり、次第にそのポジションにやりがいを見出していった梨田氏。プロ野球の世界を強く意識し始めたのは中学3年、実の父が急逝してからだったという。その後は地元・島根県の浜田高校に進み甲子園にも出場。そのときの活躍や強肩であることが評価されて1971年、ドラフト2位で近鉄バファローズに入団する。
「僕は島根県の田舎町出身ということもあり、近鉄バファローズの本拠地だった『大阪』の街になかなか馴染めませんでした。田舎育ちの純朴な青年にとって、コテコテの大阪弁は色々な意味で衝撃でしたね(笑)。それと印象に残っているのは“水”でしょうか。自然豊かな浜田の水はとても美味しかったんですけど、大阪の水はカルキの匂いがきつくて・・・洗顔や歯磨きも抵抗があって、生活すること自体が一苦労だったという記憶がありますね。
技術的なことを言えば、当然のことながら高校野球とのレベルの違いに愕然としました。高校3年の2月、卒業する前に初めて近鉄の宮崎県・延岡キャンプに参加したんですけど、まず驚いたのがスピード。打撃練習の投手がテンポ良く軽快に投じているようでいて、島根の地区予選で戦った投手の全力投球と同じくらいの球速があるのです。僕も打席に立ったのですが、そんなことだから打球は前にすら飛ばない。手袋は高くて買えず素手でバットを握るものだから、2月の寒い時期で手が腫れるんですよ。それは痛かったですね。コーチからは『手袋は破けたら終わりだけど手の皮は本革だ。頑張れ』なんて励まされながら、必死にバットを振り続けたことを覚えています。
プロ入り2年目からは、守備と肩が良かったこともあって少しずつ一軍の試合に出してもらえるようになったんですよ。ただ、バッティングが悪かった。ウィークポイントを改善したいと思って試行錯誤の末に編み出したのが、いわゆる“コンニャク打法”です。これは、前屈みになって両腕をクネクネと動かす変則フォームで、そんな極端な構えをした打者は後にも先にも僕しかいません。見た目は決して格好のいいものではありませんでしたが、少しずつ結果がついてきたのは嬉しかったですね。
実は“コンニャク打法”はコーチの助言でなく、自分の頭で考え出したんです。トリッキーなことを教えて失敗したら責任を取らねばなりませんから、指導する側はそうした冒険を怖れるもの。だからこそ「自ら考え実行する」ということは、野球だけでなくどんな世界においても非常に大事なことだと思いましたね。個性的なフォームの野茂英雄投手やイチロー選手がメジャーリーグで大活躍できたのは、誰にも真似できない自分だけのスタイルを自分でつくり上げたということも大きいのではないでしょうか」
ライバルとの関係性
梨田氏がプロ入りした翌1972年、社会人チーム・新日本製鐵八幡所属の有田修三捕手が近鉄にドラフト2位で入団する。年齢は梨田氏よりも2歳上。のちに「あり(有)なし(梨)コンビ」と呼ばれ、同チームの捕手として高いレベルで争いながら併用されることになるのだが、梨田氏はチーム内のライバルとどのように向き合ってきたのだろうか。
「有田さんは山口県出身。僕が高校1年のとき3年だった有田さんは、実力を持った捕手としてすでに名の知れた存在でした。同じ山陰地方の選手ですし、僕も当時から凄い選手だなと思って見ていたんです。それが気がつけば同チームのライバル関係になるわけでしょう。僕が入団したとき、スカウトの方から『ドラフト2位で梨田を獲得したから向こう10年は捕手を獲らなくていいだろう』なんて言われていたこともあって、色々な意味で複雑な心境でした(笑)。
実際にそれから10年以上にわたり、有田さんと併用される時期が続いたんですけど、正直、最初の頃は面白くないわけですよね(笑)。ゲームに出ないと給料が上がらないし経験も積めないわけですから。でも、それで腐っていても仕方がない。とにかくプラスに考えて、有田さんが試合に出ているあいだは脳をフル回転させて『僕ならこんな球を投げさせる』とか、『こういうふうにリードする』とか、とにかく頭のなかで色々とシミュレーションするようにしたんです。身体を動かさないのであれば頭を動かそうと。その繰り返しによって観察眼や洞察力を養うことができましたから、結果として非常にいい勉強になりましたよね。
ちなみに僕の捕手としての信念は『投手のいい部分を引き出す』こと。ピッチャーは精神力が強そうに見えて、ピンチになると落ち着きがなくなったり怯えてしまうタイプも意外に多い。だから僕はとにかく投手を安心させ、自信を持たせるよう心がけました。逆に有田さんは勝ち気なリードで、闘争心を刺激することで投手の能力を引き出していた。自分にはできない発想という意味で、有田さんから得たものは大きかったですね」
チーム内のライバルが有田捕手なら、チーム外のライバルは世界の盗塁王・福本豊選手。福本選手に盗塁を許さないため、数々の工夫をしてきたという。
「僕は肩の強さには自信があって、相手が盗塁を試みた際にセカンドへ投げるとき、マウンドに立つピッチャーのベルトあたりの高さを保ったまま糸を引くような送球ができたんですよ。しかしあるときファールチップが当たって右手を骨折し、肩の強さが失われてしまった。それならばほかの部分で肩の強さを補おうと考えたんですね。
まず、盗塁を刺すためには4つの要素がある。『肩の強さ』『スローイングまでの早さ』『コントロールの良さ』『送球の回転の良さ』。つまり『肩の強さ』以外の部分の能力を高めようと試みたんです。そのために取り組んだのは、キャッチャーミットでボールを受ける位置を工夫することでした。どういうことかというと、僕の感覚だとミットの真ん中はコンクリート。ボールを受けたとき、跳ね返る力も強いんです。ミットの先っぽの柔らかいところはベニヤ板。反発せずにストンと下に落ちます。ということは、投げる右手に近い位置でミットの先に当てて捕球すれば、最短距離でスローできるわけです。
この技術を身に付けたことで高い盗塁阻止率を維持することができ、1979?1981年にはベストナインにも選出して頂くことができました。どの世界においても言えることだと思いますが、プロ意識を持ったうえでちょっとした工夫やこだわりを積み重ねていくことで、必ずいい結果に繋がっていくと思います」