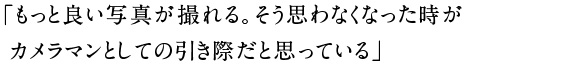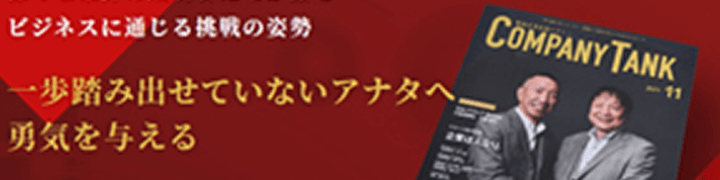巻頭企画天馬空を行く

![]()
青木 紘二 Koji Aoki
株式会社 アフロ
代表取締役
富山県魚津市出身。医院を経営する父の教育方針のもと、図書と映画に囲まれた少年時代を過ごす。高校卒業後、ヨーロッパ映画の真髄を理解すべくスイスの学校に留学し、哲学や宗教観を学ぶ。卒業後はスイス公認のスキーインストラクターとして働いていたが、帰国してフリーカメラマンに。スイス滞在中の経験と語学力を活かし、主に海外を拠点にして活躍する。1980年に「アフロフォトエージェンシー」を設立。今もプロカメラマンとして活動するプレイングマネージャーである。
写真素材やニュース・動画など、幅広いコンテンツを取り扱い、広告・出版・テレビ業界へ提供している(株)アフロ。その写真、1枚1枚の裏にはストーリーがある。
例えば、2002年のソルトレイクシティオリンピック。「奇跡の金メダル」と言われたフィギュアスケート選手、サラ・ヒューズを収めた1枚には、ジャンプをしながら天使のような微笑を浮かべる彼女が写る。この写真は世界中から評価され、メディアにも多数掲載された。しかし、カメラマン・青木がこの写真を撮影した場所はプレス席のなかでも最もコンディションが悪いと言われる「末席」。当初良いポジションを確保していたのにもかかわらず所用で席を外している間に他のカメラマンに横取りされてしまったという。「言い争いになれば心が乱れ、良い写真も撮れなくなる」。そう判断した青木氏が冷静にシャッターを切った1枚だった。
青木氏は現在、様々な大学の非常勤講師としても活動している。そのなかで繰り返し伝えているのは、「与えられた環境が満足いくものでなくても、決して諦めてはいけない」。不満を口にするくらいなら、与えられた環境のなかで、自分が何をすることができるか、あるいはどうしたらこの逆境を切り抜けられるかを考えるほうがよほど建設的だ。
定められた環境のなかで、いかに良いものを生み出すか─、その姿勢を貫き世界に写真を提供し続ける氏に、仕事に懸ける想いを聞いた。
![]()
インタビュー・文:吉松正人 写真:大木真明
日本の雪国から
世界の雪国へ渡った映画少年
 青木紘二(株式会社 アフロ:代表取締役)は、富山県魚津市で生まれた。父は開業医。地域住民に頼られ、親しまれるドクターであり、「市民の健康を守るのは医師の務め」との考えから、一般診療の他に学校医も務めた。しかも、学校医として得られた報酬は図書を購入する費用に充て、山間の貧しい小学校に寄贈していたというから、地域貢献の思いが強い人物であったことが窺える。
青木紘二(株式会社 アフロ:代表取締役)は、富山県魚津市で生まれた。父は開業医。地域住民に頼られ、親しまれるドクターであり、「市民の健康を守るのは医師の務め」との考えから、一般診療の他に学校医も務めた。しかも、学校医として得られた報酬は図書を購入する費用に充て、山間の貧しい小学校に寄贈していたというから、地域貢献の思いが強い人物であったことが窺える。そうした名士の子に生まれた青木は、「図書と映画に使うお金は黙って出してくれた」という恵まれた環境で育った。そのため、氏は早くから映画に傾倒。保護者の付き添いなしでは入れない映画館に1人で行っては先生に見つかり、大目玉を食らったという。
そして中学時代には「キネマ旬報」「スクリーン」といった映画評論誌にレビューを投稿するまでに。中学時代に一度、高校時代に一度、誌面に採用されたことがあり、それを機に青木の映画好きは益々熱を帯びていく。
一方で青木の父は稀代のカメラマニアでもあり、息子にも高価なカメラを買い与え、一緒に撮影するという趣味を持っていた。「父が経営する医院のレントゲン室は町医者としては大きすぎるほどでしたが、これは写真を自分たちで現像するための暗室を兼ねていたからです」
青木も小学生の頃から自分でフィルムを現像していたというから、父によって写真家の素養が養われたことは言うまでもない。
ただ、高校を卒業した青木は、進路の選択に迷った。カメラマンになるという選択肢はこの当時ない。本来なら父の跡を継いで医学の道を進むのが妥当だが、「本当に患者のために役立ちたいという思いがなければ医師になってはいけない」と常々言われていただけに、中途半端な気持ちでは医師を目指せないと悟った青木は、映画の世界で生きていこうと決意。多数観た映画のなかで、唯一その心理的背景やコンセプトが肌で理解できないヨーロッパ映画を知るため、スイスの学校へ留学した。そこで哲学や宗教観を学びつつ、余暇はスキー場でのアルバイトに精を出す。雪国で育ったこともあり、スキーはお手の物だったし、観光客の多いスイスでは客の話を通じて様々な国の事情を知ることができるからだ。
そして、学校を卒業した後は、スイスの国家が行うスキーインストラクターの試験をパスして国家認定スキー教師となる。
「スキーのインストラクターが国家認定と言うと意外に思われるかもしれませんが、観光が国の重要産業であるスイスでは、インストラクターたるもの、技術はもちろん、語学やマナーにも長けた人でなくてはなりません。そのために厳しい試験と研修が行われ、収入も地位に見合った額が保障されています」
プロカメラマンから
エージェンシー設立へ
こうしてスイスの国家認定教師となり、たくさんの友人も得た青木だが、迷ったあげく、日本人は日本で暮らしたほうが良いだろうという気持ちになった。しばらくはスキー教師をしながら日本とスイスを行き来していたが、27歳の時、突如「プロカメラマン」を宣言した。
「その頃は、映画の世界で食べていく夢は半ば諦めていました。かと言って一生スキーのインストラクターで終えるのは違うと思った。父は『事業を興すなら支援してやる』と言ってくれましたが、商売人になるのも違うなあって思ったんです」
プロカメラマンに資格があるわけではない。仕事にありつけようがありつけまいが、「プロ」と宣言すればプロカメラマンの誕生だ。しかし、青木には勝算があった。それは、海外事情に強く、とりわけヨーロッパのスキー場に詳しいことである。
最初は通販雑誌の「物撮り」程度の仕事しかなかったが、そのうち旅行代理店などから仕事が舞い込むように。さらに、海外のイベント撮影を頼まれた別のプロカメラマンが、語学に堪能な青木に代理出張を依頼することもあった。
転機が訪れたのはプロカメラマンを宣言して3年目のことだ。航空会社から直接の依頼を受け、アジアリゾートを撮影することに。2週間の撮影で報酬は日当4万4444円。源泉徴収税を引かれた手取りは4万円だが、当時のサラリーマンの月給が5万円程度だった時代、この報酬は破格の好待遇だ。「条件を聞いた後は、どこをどう通って自宅に帰ったか覚えていない」というほど舞い上がったのだという。
その後、スキーブームも手伝って、スキー雑誌で売れっ子のカメラマンとなった青木が、フォトエージェンシーを興したのは1980年。当時フォトエージェンシーは日本国内に300社ほどあり、「経費倒れになるからやめたほうがいい」とか「カメラマンで充分食べていけるのに、どうしてそんな無謀なことをするのか」と忠告した人も多かったという。それくらい、カメラマン・青木紘二の素質を誰もが認めていたし、有望な将来性を摘み取るようなことはさせたくないと思っていたのだろう。だが、青木本人は違う。
「自分の写真に満足していなかった。どれほど世間から認められようと、自分が満足していない作品を貸したくないし、仲間の作品のほうがよほど優れている場合もあった。だから、カメラマン仲間を説得して、写真の権利を預かったんです」
1980年9月16日。浜松町の小さなオフィスで、女性事務員1人を雇っての出発。「アフロフォトエージェンシー(後、アフロに改称)」の原点だ。